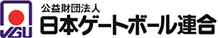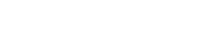2025.01.31
日本はなぜメダルに手が届かなかったのか?〜アジア大会を振り返る日本代表座談会【前編】
【前編】勝敗を分けた「熱量」と「技術力」の差
昨年12月に中国で開催された第8回アジアゲートボール選手権大会で入賞を逃した日本代表チーム。なぜ勝利をつかむことができなかったのでしょうか? 日本代表6チームの代表者の皆さんが国際大会の舞台裏を振り返りつつ、今後の課題と可能性を探ります。
前編では、華やかな開会式や緊迫の試合展開、そして海外チームとの対戦を通して感じた技術力や熱量のギャップなどについて語っていただきました。
*今大会の「競技結果」は、こちらからご覧いただけます
座談会出席の皆さん

○大垣心友会(岐阜)島田龍明主将(36・写真前列中央)
ジュニア時代から競技を続け、国スポ第1位5回など入賞多数。2016年の前回大会第3位(岐阜のチーム名)、今大会はトーナメント戦に進むも1回戦で中国のジュニアチームに惜敗

○健祥会(徳島)中村太一主将(50・写真中央)
社会福祉法人健祥会グループの職員チーム主将として全国社会人大会で通算12回優勝、3連覇中。2007年の第23回全日本選手権大会優勝。国際大会は9回目の出場で2004年の本大会と2002年世界大会で第3位。今回はリーグ戦で中国チームに破れて2勝1敗で敗退

○作新学院(栃木)片柳尚記主将(28・写真左から4人目)&岩田良文監督(51・写真右端後方)
2018&2019年全日本選手権大会V2の作新学院高校ゲートボール部卒業生を中心とするチームの主将&監督を務める部顧問教諭。本大会初挑戦でリーグ戦で中国チームに勝利するも2勝1敗で敗退

○十和田西(青森)東 亮太主将(31)
2023年全日本選手権大会優勝チーム主将。今回、国際大会初出場、リーグ戦で中国チームにパーフェクト勝利するも1勝2敗で敗退

○広島楓(広島)飯田芳幸主将(36・写真右端)
幼少の頃から競技を続け、2023年全日本選手権大会第3位。国際大会は3回目の出場で、前回大会ベスト16。今回は若手にベテランを加えた20〜70代メンバーで挑むもリーグ戦2勝1敗で敗退

○もりおか木曜クラブ(岩手)谷藤正志主将(70)
かつてグリーンピア友の会メンバーとして2002年世界大会V3を経験。以来、全国大会入賞多数。今回は10〜80代の幅広いメンバーを率いて本大会に初挑戦するもリーグ戦0勝3敗
華やかな開会式やセレモニーから垣間見えた中国の“本気”

開会式で入場行進する日本選手団
⎯⎯まず大会に参加して、開会式や審判など競技以外の点で印象残ったことからお聞かせください。
岩田 アジア大会にふさわしい豪華な開会式で、国・地域ごとの入場行進は気持ちが引き締まりました。また、国際審判員の方々のキビキビとした動き、ハキハキとしたコール、打者が10秒以内に打撃しなかったときの反則も厳格に取っていた点などが素晴らしく、日本も見習わなければと感じました。
片柳 決勝戦は、最初に選手が一人ずつ名前を紹介され、レッドカーペットを歩いてコートへ向かうというセレモニーがあって、自分もあの場に立ってみたいと思うほどに良い演出でした。
中村 中国らしい華やかな演出の開会式やセレモニーも含めて中国のゲートボールに対する熱の高さを感じました。ただ、開会式など予定時間をだいぶオーバーしていました(笑)。
谷藤 確かに時間的な感覚の違いには驚きました。逆に、コートに入ったらすぐに競技開始となったのには少し面食らいました。
東 やはり盛大な開会式がスゴイと思いました。あとは、試合ごとに中国スタッフに先導されてコートまで場内放送の音楽とともに入場行進していくスタイルで、スムーズに試合に入れたのが良かったです。
飯田 開会式も含め大会全体に選手のために開催するということが意識されていて、選手たちが楽しめる雰囲気になっていたのが良かったです。観客も含めて全員が見て楽しめる参加型のスポーツ大会を選手目線で考えてもらえていたように感じました。
島田 前日の公開練習で海外の選手から練習試合を申し込まれて、中国チーム対日本チームで試合をしたり、一緒にチームを組んで試合をしたのが、日本ではないことで新鮮で面白かったです。
ここ一番で打撃力を発揮していた中国とインドネシア

高い打撃力を発揮して日本代表の作新学院に大差で勝利したインドネシア
⎯⎯ご自分のチームの戦いを振り返りながら海外チームと対戦した感想をお聞かせください。
東 初めての国際大会だったので緊張からミスが多く、リーグ戦初日は香港と中国に負けてしまいました。ただ2日目は慣れてきてリラックスできたので、ベスト8に入った中国チームに25-5でパーフェクト勝利できたのがうれしかったです。
どの対戦チームもロングタッチを狙ってくるので、それをどう回避しながら試合を進めていこうかと考えプレーしました。日本チームと違い、かなり距離があっても、またちょっとでもラインから離れているボールがあったら狙ってくるという印象でした。
飯田 勝利した香港と台湾チームの戦い方には日本と近いものを感じました。
中国戦の相手は、準優勝チームだったんですが、リーグ戦の段階ではまだ天然芝の傾斜に対応できていなかったようでタッチもかなり外していました。だから私たちはそのミスに付け込み好試合を展開することができたんですが、そのあと逆転できなかったのが反省点ですね。
中村 唯一負けた中国戦では、相手がタッチを外したら勝てるという場面が3回ありましたが、3回とも見事にやられましたから、相手は勝負強かったです。他の中国戦を見ていても肝心な場面で決めきる強さがありました。
それと、中国チームには天然芝への抵抗感がなくなってきていると感じました。以前の中国は人工芝コート中心でしたから、国際大会でも天然芝に戸惑っている印象でしたが、今回は技術面も作戦面でもそういった戸惑いは見られず、高い技術力に合わせた作戦を展開していました。味方ボールへのつなぎ球にしても3mも離して入れたり、スライドタッチ用のボールを入れずに直接ロングタッチにいったりというのは、日本の天然芝での大会では見られない作戦でした。
また、中国はどのチームも技術力の高い選手が5人揃っていて、抜けがない印象を受けました。
谷藤 今回、自分たちのチームは参加することに意義がありといったメンバー編成で、今後の経験のために出場したこともあり、全敗という結果は予想通りでした。対戦した台湾、中国、韓国チームとも打撃技術が高く、ここ一番というところでことごとくタッチされました。技術だけでなく、精神力も高かったですね。
片柳 負けたインドネシアにはロングタッチを次々に当てられて非常に面喰らいましたが、最後の中国戦ではすでにリーグ戦敗退が決まっていたということもあり気持ちが吹っ切れて良い試合ができました。
打力自体は、日本も海外チームとそれほど変わらないと思いましたが、プレッシャーがかかる、ここぞというときの打力が不足していたように感じました。今回、自分たちもそういった場面で決めきることができなかったことが敗因の一つで、そういったところの打力差を埋めていかないと、今後も海外チームに勝つことは難しいと実感しました。
島田 リーグ戦では中国の2チームと台湾チームと対戦しましたが、公開練習を通して中国の作戦をある程度把握できていたこともあり、無理せずに勝つことができました。
トーナメント1回戦で負けた試合は、相手の中国のジュニアチーム・中国江蘇海門青少年隊の打撃が本当に上手でした。あとから、どうしたら勝てたのかと様々考えましたが、相手球を全部アウトボールにしなくては無理だったかもしれないです(笑)。作戦力でどうにかしたかったけれど難しかった。日本チームは作戦力で技術力を補うイメージなのに対して、中国チームは技術力で作戦力を補っているイメージでした。
⎯⎯細かい話になりますが、その試合では、4巡目に白8番の島田さんが第1ゲートを通過して相手球にロングタッチをして合わせ球で2球をアウトボールにするという場面がありました。その後、島田さんは、第2ゲート前方に進みましたが、第3ゲート前の赤9番にタッチして第4コーナーの赤5番に合わせ球をしてアウトボールにしていたら勝てたのでは?
島田 あのときは、自分が第3ゲート前の赤9番をねらって外したらほぼ負けは確定で、次の巡目で赤5番がプレーを失敗すれば、こちらの展開が良くなるという状況でした。人工芝コートだったら赤9番へのタッチにいったかもしれませんが、天然芝なので外す確率も高かった。当たったときのメリットを優先するか、外したときのリスクを優先させるかで、自分はリスクを先に考えて、外して負けるくらいなら相手のプレーを待とうと思ったんです。でも、5巡目の赤5番のプレーは予想以上に素晴らしく、味方3球をアウトボールにされたのはキツかったですね。
作戦力では日本が上回っていた!?

今大会でいちばん技術力が高かったと日本代表チームから絶賛されていた中国のジュニアチーム・中国江蘇海門青少年隊
⎯⎯打力が高い中国チームでとくに印象に残ったチームについて教えてください。
島田 もう圧倒的に、負けた相手の中国江蘇海門青少年隊ですね。他の中国チームも見ましたが、打力的にはいちばん上手でした。彼らは毎日8時間も練習していると聞いて、とても叶わないと思いました。自分たちは平日はなかなか練習する時間が取れないので。
東 自分も中国江蘇海門青少年隊は優勝してもおかしくないほどの技術の高さだったと思います。練習量では勝てないので、少ない練習時間の中でどう質の高い練習をしていくかが今後の課題だと痛感しました。
島田 ただ作戦に関しては、中国チームはその場その場で考えていく、言い方はわるいかもしれませんが、その場しのぎの作戦といった印象で、1巡先は苦しくなってしまうのではと感じる展開も多くありました。中国の作戦を見ていて、もっとうまくできるんじゃないかと思ってしまいました。
片柳 自分も作戦面では日本が上回っていたように思いました。日本はミスの可能性なども視野に入れながら2巡以降など長い先まで見通しながら作戦を立てるのに対して、中国やインドネシアは1巡先の決めたボールを強くするために、邪魔な相手ボールをバンバン当ててアウトボールにするという印象でした。
飯田 準優勝した中国上海市高東鎮門球隊と大会後に食事をする機会があったんですが、一緒に話をしていて感じたことは「ボールを当てることへの強い思い」でした。会話のほとんどが「あのとき当たれば勝てた」というような打撃の話題で、「あのときこういう配置だったら回避できたね」というような作戦についてはほぼ触れませんでした。中国チームが興味があるのは作戦より打撃という印象でしたね。
岩田 中国江蘇海門青少年隊をはじめ、中国チームはストイックに競技に臨んでいることが試合に現れていました。
練習量でいえば、作新学院も高校生の部活動なので毎日練習していますが、国際大会で活躍するようなチームになるには、相当のやる気と情熱、熱量がないと難しいと感じました。とくに、作新学院の場合、ほとんどの生徒がゲートボール初心者として入部してきますので、プレーが面白い、そして勝てるようになるにはかなりの練習時間を要して経験値を上げていく必要があります。
今大会に参加して、練習量が勝敗に大きく影響していることを実感しましたので、今後も引き続き、熱量とのバランスを図りながら練習に打ち込める環境をつくっていく必要があると感じました。
谷藤 中国も含めて対戦チームが今大会のためにどれだけの覚悟を持って練習したきたのかということを肌で感じることができました。ゲートボールに対する姿勢、競技に対するモチベーションが全然違いました。
*後編「日本復活への道筋はどこに? アジア大会が示した課題と未来」に続く
こちらからご覧ください