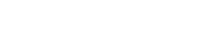2025.01.31
公式国際
日本はなぜメダルに手が届かなかったのか?〜アジア大会を振り返る日本代表座談会【後編】
【後編】日本復活への道筋はどこに? アジア大会が示した課題と未来
昨年12月に中国で開催された第8回アジアゲートボール選手権大会で入賞を逃した日本代表6チームが国際大会の舞台裏を振り返りつつ、今後の課題と可能性を探る座談会。
後編では、日本が国際大会で巻き返しを図るための強化の方向性として、勝利をつかむための戦略、技術、そして環境づくりについて未来への希望を託して語り合います。
*座談会出席の皆さんのプロフィールは、前編「勝敗を分けた“熱量“と“技術力”の差」からご覧いただけます。
こちらからご覧ください
*今大会の「競技結果」は、こちらからご覧いただけます
中国式またぎ打法は緊張感が少なく打てる大きな武器!

中国チームに多く見られた、またぎ打法によるスパーク打撃
⎯⎯前編では、海外チーム、とくに中国との“熱量”と“技術力”との差が浮き彫りになりましたが、逆に日本チームの今大会でのメンタル面はどうでしたか?
片柳 国際大会だからという特別な緊張感はありませんでしたが、メンタル面で勝ったチームとどこに差があったかといえば、やはり一打にかける集中力が劣っていたと思います。
島田 日本の大会では、大垣心友会は勝って当たり前と見られることもあり、いつもプレッシャーを感じていますが、アジア大会ではそういう目線はないので、逆に気楽にプレーできました。中国チームのメンタルの強さは練習量に裏打ちされる自信だと思います。
中村 緊張というのは、すなわちスイングのブレに現れると思います。その点、中国式のまたぎ打法は、ブレが少なく打てるという利点がありますから、その分、メンタルも強かったといえるのではないでしょうか。健祥会にもまたぎ打法の選手が数人いますが、本番の大会では3m以内のタッチを外す確率は非常に少ないです。それはヘッドを両足で挟むことによりスイングが固定されるからです。
今大会でメンバーがまたぎ打法用のシューズを購入したので見せてもらったんですが、シューズ側面がほぼまっすぐで、またぎ打法によるスパーク打撃時にボールが踏みやすいように靴底が薄く、またぎ打法がよりスムーズにできるように工夫されていました。
また、以前に、今大会にも出場していた中国の有名選手とスティックを交換したことがあるんですが、今回、彼が使用しているスティックを見たら、そのときのスティックとは全然違いシャフトがすごく柔らかいものに変わっていました。たぶん天然芝に対応させて替えたんだと思います。
このように中国の用具が打撃フォームや技術度に応じて進化していることに驚くとともに、日本でも用具を進化させていく必要があると感じました。
島田 またぎ打法はブレが少ないというのは絶対にありますね。今大会を契機として、またぎ打法に挑戦をはじめたメンバーもいます。
谷藤 うちの若いメンバーもまたぎ打法に取り組みはじめました。とくに若い選手には、中国式またぎ打法の印象は強かったようです。対戦した中国選手からも打ち方のレクチャーをいただいたようで、いま本気で取り組んでいます。ただ、両足の狭いところをスティックを通すのは難しいので、相当な打ち込みが必要でしょうね。
片柳 今後、日本の上手な選手たちがまたぎ打法がはじめると、日本全体でも流行りそうですね。
東 うちの19歳の最年少メンバーも、中国江蘇海門青少年隊のジュニア選手からまたぎ打法を教えてもらったようで、自分でも挑戦してみたいという話をしていました。
メンタル面に関しては、初の国際大会だったので、とくに1試合目は緊張して、メンバーの中には試合コートへ入場行進する際に音楽が流れていたのにも気がつかなかったという選手がいたくらいガチガチでした。
岩田 インドネシアチームは、好プレーが出るとハイタッチしたり、味方を鼓舞する声かけも大声で叫ぶほどで、アドレナリン全開で試合に臨んでいるような印象でした。集中力のために静かにプレーすることが多い日本ではマナー的にどうかと言われてしまいそうな行為ですが、そうして自分たちの緊張をほぐすことが好プレーに、ひいては勝利につながっていたように感じました。
作新学院では、とくに緊張しやすい女子選手には「チームメートへの声かけには自分の緊張を和らげる効果もある」という話をよくするのですが、今大会で海外選手が率先して行っているのを見て、あながち間違いではなかったと思うことができました。
第1ゲート未通過球が少なくなりスピーディーな試合展開に変化していた中国ゲートボール

公開練習で中国選手からまたぎ打法を教えてもらう日本代表の女子選手
⎯⎯国際大会の経験が豊富な方もいらっしゃいますが、以前と比べて、海外チームの戦い方に変化や進化が感じられた点はありましたか?
中村 2011年の改正ルール以前の「ダブル・トリプルタッチによる複数打権」のルールがあったときは、日本は複数打権のボールの組み方によって勝つことができていました。その複数打権のルールがなくなり打撃勝負になって以降、練習量の豊富な中国に負ける確率が高くなったように感じています。
谷藤 2012年に中国で開催されたジュニア交流会に参加したときに、中国チームは上がってもまた第1ゲートからリスタートする点取り方式の独自ルールで試合を行っていました。その当時から、どうしたら点数を取れるのかということをずっと追い求めてきた結果が、いまの打撃力でどんどん押し切ってくるような戦い方につながっているのかなと感じています。
島田 戦略的な点でいうと、2016年の前回大会のときに比べて、中国の作戦は少し考えて配置するようになったと感じました。それでも、日本の作戦ほどには細かく考えてはいなくて、その分を打撃力で補っていたという印象です。
飯田 今回、中国チームは第1ゲート未通過球が少なかったですね。2016年の前回大会も、2018年にブラジルで開催された世界大会でも第1ゲート未通過球の連続だったのに比べて、今回は打ち合うスピーディーな試合展開で点数を重ねていくゲートボールに変わっていました。谷藤さんがおっしゃっていた点取り方式の独自ルールが影響したのかもしれません。
島田 確かに、前回大会では第1ゲート未通過球が多かったですが、今回は、第1ゲート未通過球として残していたのは1球くらいに変わっていました。
中村 中国の得点計算機には99点まで点数が表示されるものもあるんです(笑)。その独自ルールで点数を取ろうとしたら、やはり第1ゲート未通過球をなくしますから、打ち合うゲートボールに変わり、それにともなって技術力が上がったのかもしれません。
谷藤 世界大会で日本が3連覇していた1990〜2000年代は日本の作戦力が優れていたので、中国チームに対しても威圧感は感じませんでした。しかし、今回のように、打撃力をつけた中国にことごとく当てられると、立場が逆転してしまったような印象です。究極、コート内にあるボールをすべて当てられてしまえば負けなので、何かしらの対策が必要ですね。
チーム力強化には強豪チームが切磋琢磨できる環境が必要

今大会優勝の中国江蘇多威隊。中国代表チームは大会前に6日間の強化合宿を行い今大会に臨んでいました
⎯⎯今後、日本が国際大会で巻き返しを図っていくためにはどうしたらよいか、まずはチームで考えている強化方法について教えてください。
島田 大垣心友会だけでの練習には限界があり伸びしろもないので、県外の強豪選手と緊張感を持って練習をしたり大会を行うことで、チームの技術力やメンタル面の底上げをしていかなくてはと思っています。
今回も大会前に日本代表だけでなく他の強豪チームも交えて強化合宿をするのも“あり”だったのかなと思います。実際、中国は大会前に代表チームで6日間もの強化合宿を実施したという話も聞いています。ゲートボールは経験値がものをいうスポーツなので、様々な選手と練習をするのが大切ですね。
あとは、台湾チームのように、都道府県を超えた日本選抜チームを編成することでモチベーションを上げることもできると思います。
東 今回の反省点は、経験値の少なさからくる緊張感で、それをなくすには上手な人たちと試合をして揉まれることによって大きな大会に慣れていくことだと思いました。ただ、東北地域は離れていることもあり練習会やオープン大会の機会が少ないんです。今後は、東北のゲートボールを盛り上げていくイベントみたいなものを企画したいです。
谷藤 レベルを上げていくには、やはり外に出て上手な人たちとお手合わせさせていただきながら知識や技術を吸収していく必要があります。今後は、東さんのいる青森県とも連携を取って一緒にプレーできる機会を増やしていきたいです。
片柳 作新学院も、ここ最近の反省点として対外試合を含めて練習量が以前に比べて圧倒的に少なくなっています。全国大会で良い結果を残していた頃は学生だったので毎月のように他県へ遠征に出かけていましたが、それが社会人になって難しい環境になっています。そうすると、どうしても本番の大会で緊張に弱くなってしまいます。今後はできる範囲で他県との練習会を定期的に開催してレベルアップを図っていく必要があると感じました。
中村 チームの最近の課題は、公式大会に出場するメンバーが固定化していることです。全国大会で常勝していた時は、メンバー同士で競い合い、レギュラー選手がいつも入れ替わっていました。若い選手を育てるには時間がかかりますが、そうしてチーム全体の底上げをしていく必要があります。近く、新メンバーが入る予定なので、レギュラー選手たちの刺激になればと願っています。
飯田 私たちのチームも有力チームが集まる大会には参加させていただき、勉強していきたいと考えています。
日本復活には愛好者の裾野を広げる活動も大切

日本から参加した代表6チームと国際審判員の皆さん
⎯⎯最後に、国際大会での日本復活を視野に入れて、日本全体のレベルアップを図っていくためのアイデアや提案、今後の抱負についてお聞かせください。
岩田 現在は、全日本選手権大会が国際大会に出場する日本代表チーム選考対象大会を兼ねていますが、新しい選考大会があってもいいように思います。たとえば、シングルスによる全国大会などでチームにポイントやランキングをつけると選考基準がわかりやすくなります。
飯田 チームのランキングについては今回、海外選手からよく尋ねられました。それというのも、オーストラリアや香港の代表チームは、その国・地域のランキングによって選出されていたようでした。日本でもチームのランキングを設けたら面白いと思います。
最近は、全日本選手権大会の出場チームにしても決まった顔ぶれになりつつあるので、もっと様々なチームが参加できるようにしたらと思います。各都道府県予選会には出場していないけれど、各地には強いチームや選手が大勢いますので。たとえば、前年度べスト8や都道府県選抜チームはシードで2次リーグ戦から参加するようにしたら1次リーグ戦の出場枠が空くので、都道府県の2番手、3番手チームやジュニアチームも参加できます。幅広いチームが挑戦できる大会であることが競技力のレベルアップにもつながっていくように思います。
あるいは、全日本選手権大会の上に、強豪チームによるリーグ大会を設ける手立てもあります。そのリーグに入れたらすごいということで、選手たちの高い目標にもなります。
さらには、シングルス、ダブルス、トリプルスでの全国大会なども選手のモチベーションにつながるので検討の余地があると思います。
同時に、愛好者の裾野を広げていく活動も大切です。ジュニアチームなど地域を巻き込んで自分たちより上手な選手をどんどん輩出していくことが、日本全体の底上げにもつながっていくのではないでしょうか。
片柳 日本のレベルを上げるには、時間にある程度余裕がある高校生や大学生にアプローチしていくことが大切と思います。同時に、今後の少子高齢化を考えると、定年を迎えたシニア世代の競技人口を増やすことも必要です。ジュニアとシニアの両輪で競技を支えていくことが、国内でゲートボールを発展させていく上で必要と考えています。
谷藤 現在、岩手県が抱えている課題は、若い選手をいかにして全国大会に送り出すかということです。そのためには時間や距離という負担を少なくする必要があります。たとえば全日本選手権大会の開催地を東京に固定するなどして、できるだけ全国各地から参加しやすい環境をつくることが選手たちのモチベーションにつながります。
島田 コートをたくさん設置できる広い会場に全国から様々なチームが集まり、大会だけでなく練習会や作戦の勉強会をする機会があったらいいですね。
東 海外の強豪を日本に招いて、国内からも強豪チームが集まって対戦できる大会があってもいいですね。今回、自分たちは初めて国際大会に出場して海外のレベルを実感することができたので、海外チームとの大会や勉強会があったらうれしいです。
中村 私も海外に教えを乞うときが来たように感じています。今大会では、かつての教え子たちに声を掛けられました。私は2005年頃に世界ゲートボール連合からの依頼で、台湾や韓国で技術や作戦を指導した経験があったからです。当時の海外はとくに作戦に関してはまだ発展途上でしたので。しかし、いまや立場は逆転して、総合的に見て日本は中国に劣っていると認識しなくてはなりません。当時とは逆に、今度は海外から講師を招いて海外から学ぶことも必要です。
もう一つは、ゲートボールスタジアム構想、すなわちゲートボールの聖地づくりです。2018年の世界大会でブラジルに行ったときにすごいと思ったのが会場のゲートボールスタジアムでした。クレーコートが16面ほどもある立派な専用スタジアムです。
このようなゲートボールスタジアムが日本の、それも全国から参加しやすい場所にあれば、そこで全国大会ができるし、強豪チームが集まっての勉強会、シングルスによるオープン大会なども可能になります。ゲートボールスタジアム構想には、日本でのゲートボール熱の再燃や、愛好者拡大の可能性が秘められていると思います。
撮影/伊藤 守