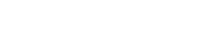2025.11.03
JGU
2025を制したトップチームたち ― 強さの裏側

11月1・2日に開催された国内最高峰の大会「文部科学大臣杯 第41回全日本ゲートボール選手権大会」では、霧島クラブ(鹿児島)が2年連続の国内チャンピオンに輝きました。
本記事では、2025年に安定した強さを見せたトップ3チームの主将たちに、練習の工夫や影響を受けた指導者、初心者へのアドバイスなど、「強さの裏側」を伺いました。
霧島クラブ(鹿児島) 楠見慎太郎主将(42)
「目標は過去の自分たちの成績。“世界”も視野に入れて一つでも多く勝ちたい」

幼少期からプレーを続け、各全国大会での入賞多数。
2025年は、全日本選手権大会2連覇、全日本世代交流大会で2度目の優勝、全国ジュニア大会2部クラスで監督として2度目の優勝。

ふだんの練習 ― 試合形式の練習で作戦の引き出しを多くつくる
個人練習のほか、チームでは月1回、3人対3人などで試合形式の練習を重ねています。
多くの場面を経験することで作戦の引き出しが増え、本番でのひらめきにもつながるからです。
技術面でも、ピンチのときに難しいスライドタッチを試したりと、打撃の精度を磨く機会にもなります。
大会前の練習 ― 会場のボールの曲がりを重点的にチェック
ふだんは人工芝コートで練習していますが、大会前はなるべく会場のコート条件に近い場所で練習するようにしています。
ただ、今年は3つの全国大会が立て続けにあったため、全日本選手権会場のような重い天然芝では練習できませんでした。
大会会場での公式練習では、距離感や転がりのスピード、特にボールの曲がりを細かくチェックします。
大会前のルーティン ― 最近は美容院に行くように
特別なことはしていませんが、最近は大会前に美容院へ行くようになりました。
全国大会で勝つことが増え、写真や動画に映る機会も多くなったので(笑)。
影響を受けた指導者 ― さつま・宮田主将の計算され尽くした作戦力
鹿児島県のさつま(宮田昇主将・2002年全日本選手権大会優勝)は、初めて「作戦がすごい」と感じたチームでした。
技術で勝つチームが多かった当時、宮田さんのボール配置は計算され尽くしており、「ゲートボールは頭脳戦だ」と教えられました。
地元大会でもご一緒する機会が多く、試合の合間に采配を観察して勉強したものです。
「一人では上手になれない。同じレベルのよいパートナーを見つけること」という宮田さんの言葉は、今も心に残っています。
参考にしているもの ― スポーツ界のトップ選手たちの表情や言葉
野球、ボクシング、テニス、サッカーなど、さまざまなスポーツを観るのが好きです。
トップ選手の表情を、自分の試合中の気持ちと重ね合わせて見ています。
最近はやはり大谷翔平選手ですね(笑)。
「不調で凹んでいる選手にこそ声をかける」という大谷選手の言葉には特に共感しました。
現在の目標 ― 世界を見据え、一つでも多く勝つこと
いまの目標は「自分たちの過去の成績を超えること」。
前身チーム・フレンドスポーツの全日本選手権3回優勝という記録を塗り替えたいと思っています。
年齢的にも体力・技術維持が課題ですが、いまのうちに一つでも多く勝ちたい。
その先には、世界も視野に入れています。
昨年のアジア大会では中国チームの強さが際立っていましたが、まだ作戦面では日本に分があります。
打撃力でそれを上回る彼らにどう対抗するか――そこが次の課題です。
ビギナーに贈るヒトコト ― 憧れの選手と良きパートナーを見つけよう
上達の近道は「憧れの選手を見つけること」。
その人のプレーを集中して見るようになり、自然と技術や作戦が磨かれます。
もう一つは、「一緒に成長できるパートナーを見つけること」。
中高生の頃、チームメートの曽山くんや、都城友の会(宮崎)の水久保くんたちと朝から晩まで練習していた時間が、今の自分をつくりました。
そして、何よりチームメートへの感謝を忘れないこと。
みんなが個々に努力を続け、控え選手も支えてくれる。
その力が、霧島クラブの強さの源だと思っています。
大垣心友会(岐阜) 島田龍明主将(36)
「練習の積み重ねが、最高の結果を呼ぶ」

ジュニア時代から競技を続け、国スポ1位5回、アジア選手権3位など多数入賞。2025年は、全日本選手権大会準優勝、国スポベスト8。

ふだんの練習 ― 週一の練習を積み上げる
全国大会で勝つには、とにかく練習の積み重ねが大事だと思います。
週1回の練習をしっかり行い、萬燈組(愛知)や志水魁(石川)などと試合形式での練習を行っています。
大会前の練習 ― 会場と同じコート条件で調整
全国大会前には、会場と同じフィールドのコートで練習するようにしています。
コート条件で作戦もかなり変わるし、メンバーのプレーの精度を把握することも必要です。
公式練習では、重さや傾斜、スパーク後のスライドタッチの感覚まで細かくチェックします。
大会前のルーティン ― 効果絶大のお守りを金神社で
とくに決まったルーティンはありませんが、公式戦前には岐阜市の金(こがね)神社でお守りを授かります。
このお守りを渡した仲間はみんなメダルを取って帰ってきたので、効果絶大です(笑)。
参考にしているチーム・選手 ― 霧島クラブ・都城友の会
霧島クラブ(鹿児島)や都城友の会(宮崎)を参考にしています。
両チームとも作戦を大事にしているので観ていても楽しく、学びが多いです。
技術・作戦の両面で参考にしているのは、霧島クラブの曽山喬貴さん。オープン大会で一緒にプレーさせていただいた経験が、今の自分の作戦につながっています。今も作戦で悩んだときは、一番に相談させてもらっている、最高の師匠のお一人です。
ほかにも、萬燈組(愛知)、作新学院(栃木)、志水魁(石川)と、たくさんのチームの試合も観させていただき、参考にしています。
影響を受けた指導者 ― 大野隆幸さん(大垣ジュニア監督)
ジュニア時代からお世話になった大野さんには、作戦とマナーの両面で教えを受けました。
「公式戦では練習の半分の力しか出せない。無理のない作戦を」との言葉はいまも忘れません。
また、あいさつや礼儀を大切にする姿勢も、大野さんから学びました。
ビギナーに贈るヒトコト ― 練習あるのみ、そして仲間を大切に
すぐに結果に結びつけるのは本当に難しいことですが、自分たちも誰にも負けないくらい練習を重ねて、今の大垣心友会があります。だからこそ、結局は「練習をひたすらするしかない」と思っています。
県内では「もう負けない」と感じることがあっても、県外に出れば“井の中の蛙”。自分より上手なプレーヤーはいくらでもいます。負けて、また練習して、また負けて――その繰り返しです。けれど、それを何度も繰り返すうちに、少しずつ上達していき、やがて自分にとって“最高の結果”を残せる日が必ず来ると思います。
そして何より、一緒にプレーしている仲間を大切にしてほしいです。ゲートボールは5人で行うスポーツ。仲間がいなければ、練習試合も大会出場もできません。ゲートボールを続けられる環境を、ぜひ大事にしてください。
技術や作戦について聞いてみたいことがあれば、気軽に声をかけてください。自分のわかる範囲であれば、できる限りお答えします。
朝霞クラブ(埼玉) 相馬嘉主将(45)
「独自のチーム路線で、強豪に挑む」

3歳から競技を始め、各全国大会で入賞多数。2025年は全日本選手権3位、国スポでは埼玉県女子監督として3度目の1位に輝く。監督・主将として6大会連続メダル獲得中。

ふだんの練習 ― 個人練習中心、試合形式は大会で代用
メンバーが現役世代・子育て世代ということもあり、チーム練習自体が難しい状況です。そのため、各自が苦手分野を個別に練習し、試合形式の練習は市大会・県大会・オープン大会で代用しています。
5人で試合形式で練習したら、一人の打撃時間はわずか数分。効率的のいい練習はできないと思います。
大会前の練習 ― 会場のコート状況を徹底的に確認
クレー・天然芝・人工芝ではボールの動き方が大きく異なるため、会場に合わせたコート条件で練習するようにしています。
会場での公開練習では、コートの速さ、傾斜による曲がり方、スパーク時のボールの沈み方、その後の打撃での跳ね方などを確認します。速さや曲がり方は打撃方向によっても異なるので、縦・横・対角方向で往復打撃を行い、コート状況の把握に注力します。
大会前のルーティン ― 大会前はとんかつ!
毎回意識しているわけではありませんが、大会前の木曜日は地元のとんかつ店でロースかつ定食を食べています。
この“とんかつジンクス”で、なんと5大会連続入賞中!
また、試合前はあえて試合と関係ない雑談をして、メンバーの緊張をほぐすようにしています。
参考にしているチーム・選手 ― 独自のチームづくりを貫く
上位チームの技術には学ぶ点も多く、憧れを抱いている方も多いと思いますが、私自身は独自の路線でチームを構築したいと考えているので、誰かを参考にすることはありません。
自分たちのチームメンバーの持ち味で、どう強豪を倒すかを考えるのが自身のスタイルです。
影響を受けた人物 ― バレンタイン監督の「猫の目打線」と「分業制」
私自身が一番影響を受けたのは、ゲートボール関係者ではなく、プロ野球・千葉ロッテマリーンズの元監督、ボビー・バレンタイン監督です。
監督・主将として全国大会のような短期決戦に臨む際、バレンタイン監督の考え方から多くを学びました。
その中でも特に印象的だったのが、「猫の目打線」と「分業制」という発想です。
「猫の目打線」は、その日の選手の調子や相手チームとの相性に応じてオーダーを柔軟に変更するというもの。
また「分業制」は、控え選手の能力をしっかり把握したうえで出場範囲を明確にし、モチベーションを保ちながら、後半にはリリーフ(救援)を投入するという考え方です。
これらの戦略は、私自身がチームを率いるうえで取り入れる大きなきっかけとなりました。
参考にしているもの ― ゴルフ・カーリング・ビリヤード
私自身もよく観るのですが、ゴルフやカーリング、ビリヤードは、ゲートボールの技術や作戦面の参考になることが多いです。
たとえば、スライドタッチの角度や強さ、ラインの読み方、また特にカーリングは相手との駆け引きや読み合いといった戦略の参考になります。
ビギナーに贈るヒトコト ー 打撃の「方向性は線、距離感は幅」を意識する
技術面では、自分の型がまだ決まっていないビギナーの方には、「方向性は線、距離感は幅」を意識することが大事だと思います。
方向性は、バックスイング・インパクト(ボールの中心を打つ)・フォロースルーのすべてが同一線上で行えると安定します。
距離感は、打撃の強さではなく、スイングの振り幅で調整すると微調整がしやすくなります。
作戦面では、「自分のチームのベストを選択する」ことを心がけています。理想のプレーを期待しても、メンバーの技術力で成功する確率が低い場合は、失敗して状況が悪化することもあるからです。
その時点で最も成功率が高い打撃を選ぶことが、勝率アップにつながると思います。
もし興味のある方がいれば、大会会場などで直接聞いてもらえれば、自分の答えられる範囲でお返事します(笑)。
「強さの裏側」取材を終えて
3人の主将に共通していたのは、「仲間への信頼」と「地道な練習の積み重ね」。
ゲートボールの奥深さと、チームスポーツとしての魅力を改めて感じさせられる取材となりました。
撮影:伊藤 守